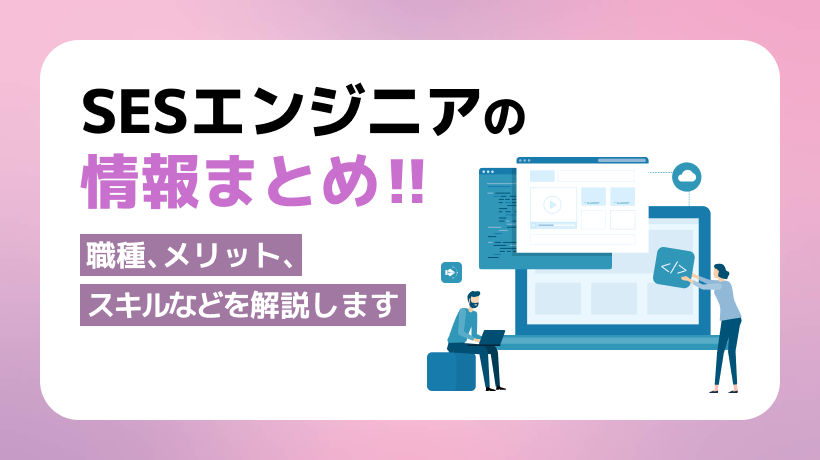「SESエンジニアとして働くのって実際どうなの?」「SESってブラックって聞くけど本当?」「フリーランスとSES、どちらがいいか知りたい」などのように考えているエンジニアの方もいるのではないでしょうか。
SES(システムエンジニアリングサービス)は、案件数の多さやスキルアップの機会が豊富な一方で、働き方や契約形態を正しく理解していないと後悔につながるケースもあります。
そこでこの記事では、SESエンジニアの雇用形態や契約、働き方、ニーズについて解説するとともに、SESエンジニアのメリット、年収、職種、キャリア形成のポイント、必要な能力について解説します。未経験でもSESエンジニアとして働けるのかどうかについても説明しているので参考にしてください。
目次
SESエンジニアとは
まず、SESエンジニアがどのような特徴があるのかを、雇用形態や働き方、SIや派遣との違いといった視点から解説します。
SESエンジニアの契約・雇用形態・働き方
SESエンジニアとは、企業と契約を結び、クライアント企業のプロジェクトに参加してシステム開発や保守・運用などの業務を行う技術者のことです。SESでは主に「準委任契約」と呼ばれる契約形態が採用されており、特定の業務を時間単位で請け負う点が特徴です。ここでは、SESエンジニアの雇用形態や働き方、さらにSIや派遣との違いについて詳しく解説します。
SESは「準委任契約」を基盤としており、業務の成果物ではなく、エンジニアが提供する労働時間に対して報酬が支払われる仕組みです。雇用形態としては、SES企業(受託会社)に正社員として雇用されるケースが一般的ですが、契約社員や業務委託として働く場合もあります。
働き方としては、SES企業に雇用されたエンジニアがクライアント先に常駐し、その企業のチームの一員として業務を進めるスタイルが中心です。案件は数ヶ月から数年単位で変わることが多く、さまざまな開発環境やチームに関わることで幅広い経験を積める点が大きな特徴です。
SESエンジニアとSI・派遣の違い
SESに似た仕組みに、SI(システムインテグレーター)と人材派遣がありますが、これらの契約形態や働き方には大きな違いがあります。
まず、SIはクライアントから業務を一括して請け負い、成果物の納品を目的とする「請負契約」を採用しています。SI企業はシステム設計から開発、テスト、納品までを自社内で完結させるケースが多く、エンジニアは基本的に社内で作業します。
一方、人材派遣は「労働者派遣契約」に基づき、派遣スタッフが派遣先企業の指揮命令のもとで働くスタイルです。派遣先企業が業務内容や進め方を直接指示できる点が特徴で、労働時間や勤務管理も派遣先が担います。
これに対してSESは「準委任契約」となり、成果物ではなく、作業の遂行そのものに対して契約を結ぶ仕組みです。SESエンジニアはクライアント先に常駐しますが、あくまで業務の指揮管理はSES企業側が行い、クライアントは作業の進行や結果に対して責任を負いません。この点が派遣との大きな違いです。
SESエンジニアのニーズは大きい?
SESエンジニアのニーズはどのようなものなのでしょうか。ここでは調査データなどをもとにニーズについて考えてみます。
エンジニアは不足している
近年、エンジニアの人材不足が深刻化しています。経済産業省の調査によると、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足する可能性があると予測されています。これはデジタル化の進展やDXの推進により、システム開発や運用を担うエンジニアの需要が急速に高まっているためと考えられています。
また、「ITエンジニア採用の実態と課題」に関する調査では、「現状、採用したい人数との間にどれくらいギャップがありますか?」という質問に対し、52.1%が「若干の不足がある」、さらに11.3%が「大幅に不足している」と回答しています。この結果からも、多くの企業がエンジニアの確保に課題を抱えていることがわかります。
SESエンジニアのニーズ
エンジニア不足が深刻化する中で、企業におけるSESエンジニアのニーズはますます高まっています。「ITエンジニアの外部人材活用の実態」に関する調査によると、「外部人材(派遣・SES・業務委託)の採用について、前年度と比べて今後どのように考えているか」という質問に対し、51.1%の企業が「積極的に活用する」、46.6%が「活用する」と回答しています。つまり、ほぼすべての企業が外部人材の活用を前向きに検討している状況です。
さらに、「ITエンジニア採用の実態と課題」に関する調査では、「人材不足を埋めるために行っている施策」として、43.5%の企業が外部人材の活用を挙げています。特に、1~10名規模でエンジニアが不足している企業が多く、こうした“ボリュームゾーン”を補うためにSESが選ばれるケースが増加しています。
このように、エンジニア不足を補うための施策としてSESが注目されており、そのニーズは今後も高まることが予想されます。
SESエンジニアの年収
SESエンジニアの年収はどの程度なのでしょうか。現役ITエンジニアを対象にした年収実態調査によると、開発形態別の平均年収は、自社開発が538万円、受託開発が512万円に対し、SES(客先常駐型)は468万円とやや低めの水準です。この結果から、SESエンジニアの給与は全体的に控えめであることがわかります。
しかし近年では、SESエンジニアの報酬も徐々に改善されてきています。これまでSESの年収が低くなりやすい理由として、「中間マージンの存在」や「スキルや経験による評価の幅が狭いこと」などが挙げられてきましたが、企業間の競争激化やエンジニア不足の影響で、こうした状況も是正されつつあります。特に、高度な技術力や豊富な経験を持つSESエンジニアは、高単価の案件を任されるケースが増えており、年収が大幅にアップする例も出ています。
ただ、SESよりもフリーランスエンジニアのほうが報酬が良い傾向にあるので、収入にこだわりたいという人はフリーランスを目指すのもよいかもしれません。
『フリーランスエンジニアの単価相場とは?職種別、業界別の相場も紹介』
SESエンジニアのメリット
SESエンジニアのメリットとはどのようなものでしょうか。
スキルを高めやすい
SESエンジニアのメリットのひとつは、幅広いスキルを身につけやすいことです。SESでは、案件ごとに異なるクライアント企業に常駐し、さまざまな開発環境やプロジェクトに携わることが多いため、短期間で多彩な業務経験を積むことができます。
また、プロジェクトの内容も多岐にわたるため、プログラミングやインフラ構築、運用保守など、特定分野に偏らないスキルセットを形成しやすいのが特徴です。これにより、最新技術やトレンドに触れる機会が増え、エンジニアとしての市場価値を高めることにつながります。
さらに、異なるチームや文化で仕事をすることで、コミュニケーション能力や適応力も自然と養われ、将来的にリーダーやマネジメント職へのキャリアアップも目指しやすくなるでしょう。
つながりや人脈を築きやすい
SESエンジニアは、多様な現場で働く中でつながりや人脈を築きやすいのが大きな特徴です。
案件ごとに異なる企業に常駐するため、現場ごとにさまざまなエンジニアや関係者と協力しながら業務を進める機会が豊富にあります。こうした環境では、通常の社内勤務では出会えない人たちと関係を築けるため、技術的な情報交換やキャリア相談に役立つネットワークが自然と広がります。将来的に転職や独立を目指す際にも、これらの人脈が大きな強みになるでしょう。
さらに、経験豊富なエンジニアやプロジェクトマネージャーと仕事を共にすることで、実践的なノウハウや業界の最新動向を学べるのも大きなメリットです。人脈が広がることでキャリアの選択肢が増え、長期的な成長やキャリアアップにもつながりやすくなるでしょう。
リスク回避がしやすい
SESエンジニアは、キャリア形成においてリスク回避がしやすい働き方といえます。
SESでは、案件ごとに異なる企業やプロジェクトで経験を積めるため、万が一特定の現場が自分に合わなくても、次の案件で環境を変えることが可能です。また、SES企業の正社員として雇用されるケースが多いため、プロジェクトの契約が終了しても給与が保証されるなど、経済的リスクを軽減できる仕組みが整っています。
「SESは現場を転々とするので不安定では?」と考える人もいますが、実際は多くのSES企業が次の案件先を積極的に用意してくれます。さらに、プロジェクトが終了しても自社待機中の給与を支払う「待機保証」を設けている企業もあり、安心してスキルアップに専念できます。リスク分散がしやすいのがSESの特徴なのです。
SESエンジニアの将来性
では、SESエンジニアの将来性はどうなのでしょうか。
SESエンジニアは、エンジニアの人材需要の増加に伴い、今後も一定のニーズが見込まれます。日本国内ではDXの推進やシステム内製化の動きが進んでおり、エンジニア不足は今後も続くと予想されます。そのため、開発リソースを補う手段としてSESの活用は引き続き重要な役割を果たすでしょう。
さらに、エンジニア側にとってもSESで働くメリットは少なくないので、SESを志す人は絶えないと思われます。SESで培ったスキルを活かし、将来的にフリーランスとして独立したり、受託開発やコンサルティングといった分野にキャリアを広げる人も増えるでしょう。
このように、SESエンジニアは長期的な需要が期待される職種です。今後も技術の進化に対応できるエンジニアであれば、SESを通じて安定した活躍の場を確保できるでしょう。
SESエンジニアの職種
SESとして働くエンジニアには、さまざまな職種があります。SESでは、クライアント企業の開発現場に常駐して業務を行うため、プロジェクトの内容やフェーズによって求められるスキルや役割が異なります。ここでは、各職種の仕事内容や特徴、求められるスキルについて詳しく解説していきます。
プログラマー
プログラマーは、SESエンジニアの中でも最も基本的な職種のひとつであり、クライアントが提示する仕様書や設計書に基づいてプログラムの実装を担当する職種です。具体的には、Webシステムや業務アプリケーション、組み込みソフトなど、さまざまな分野のコードを書く作業を行います。
案件によって使用する言語は異なりますが、Java、Python、PHP、JavaScript、C#、Rubyなどが多く使われています。開発環境やフレームワークにも一定の理解が必要で、実装だけでなく、単体テストや不具合修正まで含めて担当するケースが一般的です。
プログラマーとしての土台を築くことは、SESエンジニアとして長く活躍するための第一歩となります。
SE
システムエンジニア(SE)は、プログラマーよりも上流工程に携わる職種で、クライアントの要望をヒアリングし、それをもとにシステムの仕様を設計する役割を担います。SESの現場では、設計書の作成、要件定義、基本設計・詳細設計などを中心に行い、場合によっては進捗管理や品質管理などのマネジメント業務も任されることがあります。
SEには、開発言語やフレームワークなどの技術的知識に加えて、業務理解力やドキュメント作成スキルなどが求められます。SESエンジニアとして経験を積んだ後、SEにステップアップすることで、より上流工程に携わりながらスキルの幅を広げていくことができるでしょう。
Webエンジニア
Webエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションの設計・開発・運用を行う職種で、SES案件でも多くの需要があります。主にフロントエンドとバックエンドのいずれか、または両方に関わることが多く、HTML/CSS、JavaScript、PHP、Python、Rubyなどの言語や、React・Vue.js・Laravel・Node.jsなどのフレームワークを使った開発が主な業務となります。
Webエンジニアとして求められるスキルには、プログラミング言語の実装力だけでなく、UI/UXへの理解、セキュリティ対策、チーム開発に必要なGitなどのツールの活用スキルも含まれます。また、常に進化するWeb技術に対応するため、自主的に学び続ける姿勢も重要です。
SESとしてWeb開発に携わることで、最新の開発環境や多様な業界の案件に触れる機会が得られ、スキルの幅を広げることができるでしょう。
サーバーエンジニア
サーバーエンジニアは、企業のITインフラを支えるサーバーの構築・運用・保守を担当する職種です。SESにおいても、特に大規模システムや24時間稼働が求められる業界では需要が高く、インフラ系エンジニアの中核を担う存在です。
主な業務内容としては、物理サーバーや仮想サーバーの設定、OSのインストール・初期設定、ネットワークとの連携、セキュリティ対策、ログ管理、障害対応などが挙げられます。近年では、オンプレミス環境だけでなく、AWSやAzure、GCPといったクラウド環境の構築・運用も重要な業務の一部となっています。
SESとしてさまざまな現場を経験することで、スキルと知見を着実に積み上げることができる職種といえるでしょう。
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアは、企業の情報システムを支えるネットワークの設計・構築・運用・保守を担当する職種です。SESとして働く場合は、クライアント先の社内ネットワークやデータセンター、クラウド環境など、さまざまな現場でのネットワークインフラに関わる業務を担います。
主な業務には、LANやWANの設計・構築、ルーターやスイッチなどのネットワーク機器の設定、ファイアウォールの設計と導入、トラブルシューティング、ネットワーク監視などがあります。また、セキュリティ対策やネットワークの最適化も重要な役割となります。
SESとして多様なネットワーク環境に携わることで、経験値が広がり、より高度なインフラエンジニアやセキュリティエンジニアへのステップアップも可能になるはずです。
『IT業界のSESについて徹底解説!メリットや未経験でも働けるかも説明します』
SESエンジニアに求められるソフトスキル
SESエンジニアは各職種において専門的な能力が必要とされますが、それ以外にソフトスキルが求められます。
プロとしての姿勢、スキル
SESエンジニアとして活躍するためには、プロとしての姿勢やスキルを身につけることが不可欠です。SESエンジニアは、自社ではなくクライアント先で働くケースが多く、常に“外部のプロ”としての立場で業務にあたる必要があります。そのため、専門的なスキルに加えて、課題に対して主体的に取り組む姿勢や、信頼される人間性が求められます。
実際、「プロフェッショナルとして、課題解決に向き合ってくれる」ことを期待する企業が45.1%に上るというデータもあります。また、スキルや経験年数に見合った技術力を持たないエンジニアに対しては、「経験年数に見合った技術スキルではなかった」と感じるクライアントが38.9%存在しています。このことからも、SESエンジニアには技術力と姿勢の両方が求められていることがわかります。
コミュニケーション力
SESエンジニアとして成功するためには、コミュニケーション力が欠かせません。
SESエンジニアは、社内メンバーだけでなく、クライアント企業の担当者や他社の技術者とも連携して業務を行う場面が多くあります。そのため、円滑に情報を共有し、誤解なく意思疎通を図るスキルが求められます。特に、顧客対応の場面では、技術力と同じくらい、相手の要望を正確に理解し、丁寧に応える力が求められます。
上のデータでも、「個人としては能力があるがチームとして成果を出せる人材ではなかった」という理由で評価を下げたケースが48.4%に上っており、「コミュニケーション能力が期待に合わなかった」との回答も38.3%を占めています。SESエンジニアとして信頼され成果を出し続けるためには、顧客対応を含めた高いコミュニケーション力が重要なのです。
マネジメントスキル
SESエンジニアとしてキャリアを築くうえで、マネジメントスキルを身につけることは有効です。
SESエンジニアは、現場での業務経験を重ねる中でリーダーやサブリーダーといったポジションを任されることがあります。その際、チームをまとめる力や、タスクの進捗管理、メンバー間の調整力といったマネジメントスキルが求められます。単に技術者としての能力にとどまらず、組織的な成果を出す力が、クライアントからの信頼や評価にも直結するのです。
SESエンジニアが継続的に信頼され、リーダーとして活躍していくためには、マネジメントスキルを高めておくことが重要です。
SES企業を選ぶ際のポイント
SESエンジニアとして働くためには、SES企業に所属する必要がありますが、SES企業を選ぶときにはどのようなポイントに気をつければよいのでしょうか。
希望する案件やスキル領域があるか
SES企業を選ぶ際には、自分の希望する案件やスキル領域に合致した案件があるかどうかを確認することが重要です。
SESエンジニアは企業から提示されるプロジェクトに参加するスタイルで働くため、どのような案件に参画できるかが将来のキャリアやスキル習得に大きく影響します。自分の志向と異なる案件ばかりを担当していては、目指すキャリアから遠ざかってしまうでしょう。
自分の希望分野に強いパイプを持つ企業を選べば、成長機会が多く、スキルアップもしやすくなります。SES企業に希望する案件やスキル領域に関する取り扱いがあるかを事前に確認することで、理想的なキャリアを実現しやすくなるはずです。
契約形態や労働条件の透明性
SES企業を選ぶ際には、契約形態や労働条件が透明であるかどうかをしっかり確認しましょう。
契約内容が不明瞭なまま就業すると、想定していた給与や勤務時間、仕事内容とのギャップが生じるリスクがあります。特にSES業界では「偽装請負」や「多重下請け構造」といった問題が存在するケースもあり、労働条件に関するトラブルを避けるためには、企業が提示する情報の透明性が大きな判断材料になります。
SES企業を選ぶ際は、契約の種類や雇用形態、報酬の還元率、残業代の有無、有給休暇の取得実績などを事前に把握するようにしましょう。
サポート体制やフォローアップの有無
SES企業を選ぶ際には、サポート体制やフォローアップの有無を確認することが大事です。
エンジニアが安心して業務に取り組むためには、現場配属後も定期的な面談やキャリア相談など、企業側からの継続的なサポートが不可欠です。特にSES業界では、エンジニアが孤立しやすい傾向があるため、企業のフォロー体制が充実しているかどうかが、働きやすさを左右します。
定期的なキャリア面談や資格取得支援、トラブル時の相談窓口の設置、メンター制度の有無などを確認しましょう。
単価や報酬の仕組み
SES企業を選ぶ際には、単価や報酬の仕組みをしっかりと確認することが重要です。
同じ案件であってもSES企業ごとに報酬の取り分やマージンの開示方法が異なり、自身の収入に大きく影響します。マージン率が不明瞭な企業を選んでしまうと、自分の働きに対して適切な報酬が得られないリスクもあるので注意しなくてはなりません。エンジニアへの還元率やマージンの開示有無、契約単価の明示、支払サイトなどを確認しておくことで、自分の働きに見合った報酬を確保しやすくなるでしょう。
このように、SES企業を選ぶ際は、単価の金額だけでなく、その内訳や報酬の仕組み全体をしっかり確認することで、自分に合った納得のいく条件で働くことができるはずです。
キャリアアップや教育制度の有無
SES企業を選ぶ際には、キャリアアップ支援や教育制度の有無を確認することが重要です。
エンジニアとして継続的に成長し、市場価値を高めていくためには、企業側のサポート体制が大きく影響します。特にSESの働き方では、客先常駐が多く、企業からの直接的な支援が受けにくい場合もあるため、教育制度やスキルアップ支援が整っているかどうかが、将来的なキャリアに直結します。
定期的な技術研修、eラーニング、外部セミナー費用の補助、資格取得支援などがあるかどうかを確認しましょう。また、将来のポジション設計の機会があるかどうかも確認ポイントです。これがある企業は、単なる現場派遣にとどまらず、社員の成長と定着を重視している傾向にあります。
未経験でもSESエンジニアとして働ける?
SESエンジニアの仕事内容やキャリアについて解説してきましたが、実務経験のない未経験のエンジニアでもSESとして働けるのでしょうか。
結論から言えば、未経験でもSESエンジニアとして働ける可能性は十分にあります。実際、「ITエンジニアの外部人材活用の実態」に関する調査によると、SES企業の約48.6%が未経験者を採用しているようです。
中でも、「コミュニケーション力や意欲などソフト面が重要と考えたため(45.4%)」という理由で未経験者を採用している企業が最も多いですし、「知識があれば、実務はキャッチアップすれば問題ない(42.8%)」という回答も多く見られました。
つまり、基本的な知識や学習意欲があること、そして現場で円滑にコミュニケーションを取れるスキルがあれば、実務未経験でもSESとしてのキャリアをスタートさせることができる可能性があります。未経験からIT業界へ第一歩を踏み出したい方にとっては、SESという働き方は有力な選択肢となるでしょう。
SESエンジニア、フリーランスエンジニアとして働くならベスキャリITで
SESエンジニアは、安定したニーズが見込まれ、スキルアップの機会にも恵まれている働き方です。しかし一方で、契約内容の不透明さや年収の低さ、希望する案件とのミスマッチといった課題もあります。そういったリスクを避けるためには、フリーランスエンジニアもおすすめです。
フリーランスエンジニアであれば、自分のスキルや希望条件に合った案件を選びやすく、報酬面でも納得のいく契約ができる可能性が高まります。特に中間マージンが少ない直請け案件などを選べば、SESよりも高い収入を得ることも十分に可能です。また、働く時間や場所を自分でコントロールできるため、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方も実現しやすくなります。そして、フリーランスとして安定したキャリアを築きたい方には、「ベスキャリIT」がおすすめです。
ベスキャリITは、フリーランスに特化したエージェントです。運営歴は15年以上あり、長年にわたって数多くのITエンジニアのキャリアをサポートしてきた実績があります。常時10,000件以上の案件を保有しており、高単価案件ながら、週2〜3やリモートの案件など、多様な働き方に対応した案件を取り扱っています。
さらに、業界に精通したコンサルタントが、スキルや希望条件に合わせて最適な案件を提案してくれるため、効率的に理想の案件へとつなげることができます。すでにSESなどで実務経験を積んでおり、さらなるキャリアアップや収入向上を目指したい方にとってもおすすめです。ぜひご登録ください。