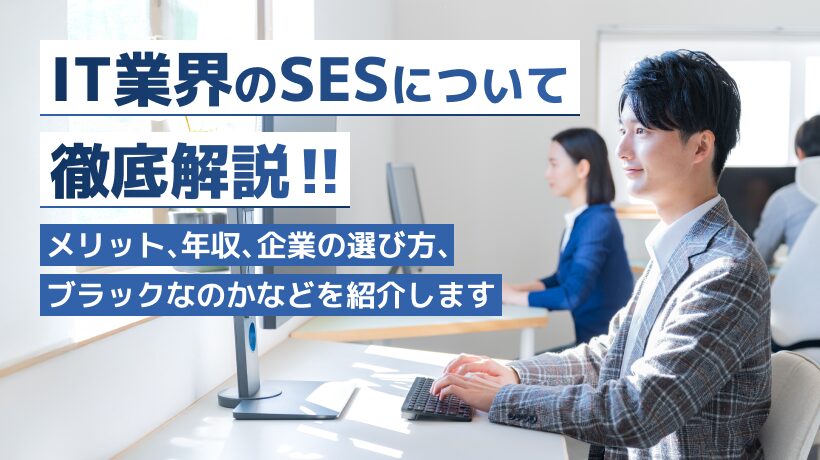「ITエンジニアとしてSESで働くメリットや注意点を知りたい」「IT業界のSESでどれくらい稼げるのか」「SESってブラック企業が多い印象だけど実際どうなの?」という疑問を持っている人も多いと思います。
SES(システムエンジニアリングサービス)は、ITエンジニアの働き方のひとつとして多くの現場で活用されていますが、業務形態や契約内容に特徴があるため、正しく理解しておかないと自分に合ったキャリア選択ができなかったり後悔する可能性があります。
この記事では、SESの基本的な仕組み、IT業界におけるSESのニーズ、SES企業で働くメリット、SESとして働くときに求められること、SES企業の選び方について詳しく解説していきたいと思います。
目次
SESとは
まずはSESがどのようなサービスなのか、SIとの違いについて解説します。
SESの意味
SESとは、ITエンジニアがクライアント企業に常駐し、システム開発や運用、保守といった業務を支援する契約形態です。雇用主であるSES企業と、業務を提供するクライアント企業との間で準委任契約を結ぶ形が一般的で、成果物ではなく業務遂行そのものに対して報酬が支払われます。
SEやプログラマー、Webエンジニア、ネットワークエンジニア、サーバーエンジニア、データベースエンジニアなど、幅広い職種のエンジニアがSESとして活躍しており、プロジェクト単位でさまざまな現場に携わることができるのが特徴です。特定の業種や工程に特化した案件も多く、自身のスキルやキャリア志向に合った働き方が選べる一方で、常駐先の環境によって業務内容や働き方に差が出ることもあります。
SESとSIの違い
SESとSI(システムインテグレーション)は、いずれも企業のシステム開発や運用を支援するITサービスですが、契約形態や業務の進め方に明確な違いがあります。
SESは「準委任契約」に基づき、エンジニアがクライアント企業に常駐して業務をサポートする形態です。成果物ではなく、人的リソースの提供に焦点を当てており、設計・開発・テスト・運用保守といったプロジェクトの一部工程に対応します。報酬は、稼働時間や業務内容に応じて支払われるのが一般的です。
これに対して、SIは「請負契約」が中心で、クライアントの要件に基づいてシステムの企画から設計・開発・導入までを一括で請け負う形です。SIer(システムインテグレーター)と呼ばれる企業が主導し、納期・品質・コストに対する責任を負いながら、最終的な成果物を納品します。
つまり、SESは「人を提供する」サービス、SIは「システムを構築して納品する」サービスと捉えることができます。それぞれに適した用途があるため、プロジェクトの内容や体制に応じて使い分けることが重要です。
SES契約と各種契約形態の違い
SES契約の準委任契約以外に、エンジニアの働き方や契約形態には、「請負契約」や「派遣契約」があります。それぞれの契約形態の違いは以下です。それぞれの契約形態の違いは以下です。
| 契約形態 | 指揮命令権 | 成果物の有無 | 契約の目的 |
|---|---|---|---|
| SES (準委任契約) |
SES企業にあり (クライアントは指示不可) |
なし (業務の遂行が目的) |
労働力の提供・業務支援 |
| 請負契約 | 請負会社にあり | あり (成果物に対して報酬) |
成果物の納品 |
| 派遣契約 | クライアントにあり | なし | 労働力の提供 |
準委任契約では成果物の納品ではなく、エンジニアが一定の業務を遂行することが目的です。現場での指示命令はSES企業にあるため、クライアントは直接指示を出すことができません。
一方、請負契約は成果物に対して責任を持つ契約形態で、成果の完成が報酬支払いの条件になります。請負会社がプロジェクトを主導し、完成責任も負います。派遣契約では、派遣された労働者に対する指揮命令権はクライアント側にあります。労働力の提供が目的であり、業務の進行や管理もクライアントが行います。
これらの違いを理解しておくことで、プロジェクトや業務の性質に応じて最適な契約形態を選ぶことができます。特にSES契約を導入する際は、契約上の責任範囲や指揮系統に注意する必要があります。
IT業界におけるSESのニーズ
IT業界におけるSESのニーズは、どのような状況なのでしょうか。データをもとに、現状について解説します。
エンジニアは不足している
IT業界では、深刻なエンジニア不足が続いています。経済産業省の調査によれば、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されています。これは、ITの急速な進化やDXの加速に対して、供給できるエンジニア数が追いつかないためです。
さらに、企業側もその人材不足を実感しています。「ITエンジニア採用の実態と課題」に関する調査では、企業の63.4%が「若干の不足がある(52.1%)」または「大幅に不足している(11.3%)」と回答。つまり、採用目標に対して必要な人材を確保できていない企業が多数存在することがわかります。
このように、エンジニアは不足しており、企業はあらゆる手段で人材確保に取り組まざるを得ない状況にあるのです。
SESのニーズ
SESのニーズについても、データからその高まりが明らかになっています。
「ITエンジニアの外部人材活用の実態」に関する調査では、「外部人材(派遣・SES・業務委託)の採用について、前年度と比べてどう考えているか」という問いに対し、「積極的に活用する(51.1%)」「活用する(46.6%)」と、ほぼすべての企業が前向きな姿勢を示しました。
また、「人材不足を埋めるために行っている施策」として、43.5%の企業が「外部人材の活用」に注力していると回答しています。特に「1〜10名ほどの人材が不足している」という中小〜中堅規模の企業にとって、必要なスキルを持つ人材を柔軟に確保できるSESは有効な手段でしょう。
実際の人員構成にも、SESの活用が反映されています。企業全体で見ると、社員の約6割が正社員で、残りの4割は派遣・業務委託・SESなどの外部人材で構成されています。そのうち、SESエンジニアは約12〜15%を占めており、一定の割合で安定的に活用されていることがわかります。
このように、エンジニア不足を補う現実的な手段として、SESのニーズは確実に高まっており、今後も継続的に拡大していくと考えられるでしょう。
企業がSESを利用する背景
では、企業がSESを利用する背景とはどのようなものなのでしょうか。これは単にコスト面や外注の利便性だけではなく、企業が抱える構造的な課題に深く関係しています。
上の調査データによると、企業がSESを利用する主な理由として、最も多かった回答が「人材不足の解消(54.4%)」です。これは、社内での正社員確保が難航しており、SESを通じて即戦力の人材を外部から調達せざるを得ない状況であることを示しています。
続いて多かった理由は、「自社で育成する環境がないため(41.8%)」となっています。特に中小企業では、教育体制やメンター制度が整っていないことも多く、新卒や未経験者をイチから育てるのが困難な場合があります。そのため、スキルを持った外部エンジニアに頼る傾向が強まっていると考えられます。
さらに、「採用活動が思った通りにいかないため(35.6%)」という理由も多く挙げられており、採用市場の競争激化や、求職者の希望条件とのミスマッチが原因で、正社員採用がうまく進まない現実も浮き彫りになっています。
IT業界でSESとして働くメリット
SESのニーズが高いことはわかりましたが、IT業界でSESとして働くことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
スキルを高めやすい
SESとして働く大きなメリットのひとつは、スキルを効率的に高めやすい環境に身を置けることです。SESは、企業やプロジェクトごとに配属先が変わることが多く、さまざまな開発現場や業務フェーズを経験できます。
たとえば、ある案件ではフロントエンド開発に携わり、別の案件ではバックエンドやインフラ周辺の業務に関わるといったことも珍しくありません。こうした経験の積み重ねにより、特定分野だけでなく幅広い技術スキルや業務理解が身につくため、エンジニアとしての総合力を高めることができるのです。
また、配属先によっては最新技術を導入している企業もあり、市場価値の高いスキルやトレンドに触れる機会も得られるでしょう。特定の会社に長く勤めるよりも、短期間で多様な現場に触れることができるため、スキルアップを重視するエンジニアにとっては魅力的な働き方といえます。
つながりや人脈を築きやすい
SESとして働くことで、エンジニアとしてのつながりや人脈を築きやすくなります。
SESは案件ごとにさまざまな企業やプロジェクトに参画する働き方であり、そのたびに新しい現場や関係者と出会うことになります。このような環境に身を置くことで、自然とエンジニア仲間や業界関係者とのネットワークが広がっていくのです。同じプロジェクトに常駐している他社のエンジニアやPMとの交流から、次の案件に誘われることもあるでしょう。
また、SESとして多様な企業文化や開発スタイルに触れることで、人間関係の構築力やコミュニケーション能力も自然と磨かれていきます。これは単に人脈が広がるというだけでなく、現場で信頼されるエンジニアとして評価を得ることにもつながるはずです。
リスク回避がしやすい
SESとして働くメリットには、自分に合わない環境からのリスク回避がしやすいという点があります。
正社員として就職した場合は、職場の人間関係や業務内容が合わなくても簡単には辞めづらいのが現実ですが、SESの場合は案件ごとの契約で働くため、柔軟に現場を変えることが可能です。間に入るSES企業が調整してくれることも多いため、個人の判断で孤立せずに問題解決に向けて動ける点も安心材料でしょう。
さらに、SESでは勤務先(常駐先)と雇用元が異なるという構造上、現場に問題があった場合に直接対話すべき相手が明確であることも強みです。たとえば、過度な残業やスキルに合わない業務、ハラスメントの懸念などがあれば、SES企業に相談して別の案件への変更や契約終了といった対応を依頼することができます。
SESとして働くときに求められること
SESとして働く際にはエンジニアとしての技術力はもちろん必要ですが、それ以外にどのような要素が求められるのでしょうか。
プロとしての姿勢、スキル
SESとして働く上では、エンジニアとしての技術力だけでなく、プロフェッショナルとしての姿勢や課題解決能力も強く求められます。
「ITエンジニアの外部人材活用の実態」に関する調査によると、SESエンジニアに対して重視するポイントとして「課題解決に真摯に向き合う姿勢」(45.1%)が最も多く挙げられています。これは、クライアント先で業務を行うSESという働き方の特性上、「自社の一員」としての責任感を持ち、自ら考え行動できる姿勢が信頼獲得につながることを意味しています。
また、別の調査では、「経験年数に見合ったスキルを持っていない」という不満が38.9%の企業から寄せられており、形式的な経歴ではなく、実務に即したスキルや対応力が評価対象であることがわかります。つまり、「何年働いてきたか」ではなく、「どのような課題をどのように解決してきたか」が重視されるのです。
このように、SESとして長く活躍していくためには、課題解決力とプロ意識、そして実践的なスキルをバランスよく兼ね備えることが求められます。単なる技術者ではなく、「現場に貢献できるプロフェッショナル」であることが求められるのです。
コミュニケーション能力
SESとして現場に常駐する場合、コミュニケーション能力は重要なスキルのひとつです。社内の上司・同僚との連携に加え、顧客企業の担当者や外部パートナーとも円滑に意思疎通を図る力が求められます。特に顧客対応の場面では、相手の要望や意図を正確にくみ取り、誤解のない形で伝えるスキルが欠かせません。
上の調査では、企業が中途採用者に対して感じるギャップの中でも、「チームとして成果を出せる人材ではなかった」(48.4%)、「コミュニケーション能力が期待に合わなかった」(38.3%)といった点が多く挙げられています。これは、単に業務がこなせるだけでなく、周囲と協力しながら成果を出す姿勢や、柔軟な対話力が強く求められていることを示しています。
SESは顧客先の環境で業務を行うため、職場ごとの文化や人間関係に適応する柔軟さも求められます。自社内とは異なる環境下でも円滑に立ち回れる力は、技術以上に現場での信頼を得る大きな要素でしょう。
マネジメントスキル
SESとして働く上で、マネジメントスキルを身につけておくことも大事です。
SESでは顧客先で業務を行うため、進捗管理やタスクの優先順位付けなど、自己管理能力に加えてチームやプロジェクト全体を見渡す視点が求められます。さらに、一定の経験を積むと、チーム内の調整や後輩エンジニアの指導など、リーダー的な役割を担う機会も増えてくるため、マネジメントスキルが強く求められるのです。
マネジメント力が不足していると、連携ミスやリソース配分のズレが発生し、顧客からの信頼を損ねてしまうリスクがあります。こうした状況に柔軟に対応できるエンジニアは、SES現場で高く評価されやすい傾向があるでしょう。
IT業界のSESの年収
ITエンジニアの働き方は多様化しており、その中でもSESは広く普及しています。しかし、SESは年収が低いというイメージを持つ人も少なくありません。実際のところ、SESの年収はどのような水準なのでしょうか。
ITエンジニアの職種別平均年収に関する調査データによると、開発形態別の平均年収は、自社開発が538万円、受託開発が512万円、そしてSES(客先常駐型)は468万円となっています。この数字からもわかるように、SESは他の開発形態に比べて年収がやや低めに設定されている傾向があります。
この背景にはいくつかの要因があります。SESではエンジニアの単価に対して複数の企業が中間マージンを取る構造になっているため、実際にエンジニアに支払われる報酬が少なくなってしまうという課題があります。また、スキルや経験年数に関わらず、業務内容が単純作業に偏るケースもあり、それが給与の上がりにくさに直結している場合もあります。
とはいえ、クラウドやセキュリティ、AIといった専門性の高いスキルを持ったエンジニアは、SESでも高単価で取引されるケースが増えています。優良なSES企業では、スキルアップ支援やキャリアプランを重視した給与体系を導入しているところもあります。また、年収に重きを置く場合には、フリーランスのほうがよいかもしれません。
IT業界のSESはブラックなのか?
IT業界においてSESは、エンジニア不足を補う存在として重要な役割を担っています。しかし一方で、「SESはブラックだ」といった声も根強く存在しているのが現実です。では、なぜそのような評価がなされるのでしょうか。
退職代行サービスへの取材によると、退職代行サービスを利用する人の7~8割がSES企業の従業員であるというデータがあります。特に利用理由として多いのは、「ハラスメント」と「退職の引き留め」です。SES社員は、客先常駐という特殊な働き方ゆえに、現場での人間関係に悩んだり、雇用主であるSES企業から強引に退職を引き止められるケースが少なくないようです。
さらに問題視されているのが、スキルの不十分なエンジニアを「経歴詐称」で現場に送り込む、あるいは企業がエンジニアを直接雇用しているかのように見える「偽装請負」といった不適切な取引です。こうした行為は法令違反となる可能性があり、働く側のエンジニアにとっても大きなリスクを伴います。
このような事情から、すべてのSES企業がブラックというわけではありませんが、ブラックな環境に陥りやすい土壌があるのも事実でしょう。SESとして働くことを考える際は、企業の選定を慎重に行い、契約内容や就業環境について十分に確認することが重要です。
IT業界のSES企業の選び方
IT業界のSES企業を選ぶときには、どのような会社を選ぶべきでしょうか。
エンジニアファーストの環境が整っているか
IT業界のSES企業を選ぶ際には、エンジニアファーストの環境が整っているかどうかを確認しましょう。
エンジニアファーストの環境とは、現場で働くエンジニアの成長や働きやすさを重視した制度や風土が整っていることを指します。具体的には、スキルアップ支援、キャリア相談体制、案件の希望反映、メンタルケアの仕組みなどが挙げられます。こうした環境があれば、エンジニアは安心して業務に集中でき、長期的に活躍することができるでしょう。
例えば、「単価の高い案件にアサインされるが、希望やキャリアが考慮されない」といった企業では、モチベーション低下や早期退職につながりやすくなります。一方で、エンジニアファーストを掲げる企業では、本人の希望に沿った案件選定や定期的なフォローアップが行われており、実際に現場定着率や満足度が高い傾向があるでしょう。
契約内容と労働条件を確認する
SES企業を選ぶ際には、契約内容と労働条件を事前にしっかり確認することも重要です。
SESとして働く場合、雇用形態や契約内容によって、勤務時間、残業の有無、休日、給与体系、評価制度などが大きく異なります。内容をきちんと把握しておかないと、思っていた条件と実際の働き方にギャップが生じ、長く働き続けることが難しくなる可能性があります。
特にSESは顧客先常駐が基本となるため、自社の労働条件が不明確だと、トラブルのもとになりかねません。IT業界のSES企業を選ぶ際には、契約内容と労働条件をしっかり確認するようにしましょう。
希望する案件やスキル領域があるか
SES企業を選ぶ際には、自分が希望する案件やスキル領域に合った業務が用意されているかを確認することが大切です。
SESエンジニアとして成長し続けるためには、自分のキャリアプランに沿った案件に携わることが必要です。スキルに合わない案件ばかりだと、技術的な成長が停滞したり、モチベーションの低下を招く可能性があります。また、希望の領域での実務経験を積むことで、将来的な転職やフリーランスとしての独立にもつながるでしょう。
そのため、自分の希望するスキル領域や工程にマッチした案件があるかを確認することが重要です。まずは、SES企業の公式サイトをチェックし、どのような業界や技術分野の案件を扱っているかを確認しましょう。また、企業とのカウンセリングや面談の際には、実際に携われる案件の内容や工程、配属されるチームの体制、使用する技術スタックなどについて詳しく質問することが大切です。
営業担当やフォロー体制の質を見る
IT業界のSES企業を選ぶ際は、営業担当者の対応力やフォロー体制の質を必ず確認しておくことが重要です。
SESではエンジニアが顧客先に常駐するため、営業担当者の提案力や交渉力が、配属される案件の質や働きやすさに大きく影響します。さらに、常駐先でトラブルや不安が生じた際、迅速かつ的確に対応してくれるフォロー体制が整っていなければ、エンジニアが孤立し、ストレスを抱えるリスクも高まります。
逆に、エンジニアの希望やキャリアを理解し、丁寧にサポートしてくれる営業担当がいる企業では、安心して現場に集中でき、長期的に働き続けやすくなります。そのため、SES企業を選ぶ際には、営業担当者の対応姿勢や、フォロー体制の内容を事前に確認しておくのがよいでしょう。
評判・口コミをチェックする
SES企業を選ぶ際には、事前にその企業の評判や口コミをチェックしましょう。
口コミや評判には、求人票や公式サイトではわからない現場の実態や働きやすさに関する情報が多く含まれています。企業側の発信だけでは、実際の労働環境やフォロー体制、営業担当者の対応力などが見えにくいため、第三者のリアルな声を確認することが重要になります。
転職サイトのレビューやSNS、口コミサイトなどを参考にすることで、その企業がエンジニアを大切にしているか、キャリア支援が充実しているか、無理な常駐先へのアサインがないかといった情報を得ることができるでしょう。特に、複数の情報源からの意見を比較することで、より客観的な判断が可能になるはずです。
未経験でもIT業界でSESとして働ける?
ここまで、IT業界におけるSESについて解説してきました。SESは実務未経験でも働けるのでしょうか。
未経験者はSESとして働ける
IT業界においては、未経験者でもSESとして働ける可能性があります。
これは、エンジニア不足が深刻化する中、SES企業の多くが実務経験よりも人柄やコミュニケーション能力、学習意欲といったソフトスキルを重視しているためです。基礎的なIT知識があれば、現場での実務経験は入社後にキャッチアップできると判断されているケースも多くあります。
実際に、「ITエンジニアの外部人材活用の実態」に関する調査でも、SES企業の48.6%が未経験者を採用していると回答しており、「コミュニケーション力や意欲などソフト面が重要と考えたため」が45.4%と最も多い理由として挙げられています。また、「知識があれば、実務はキャッチアップできる」との回答も42.8%にのぼり、多くの企業がポテンシャル重視で採用している実態が見えてきます。
このように、コミュニケーション力や学習意欲があれば、未経験者でもSESとしてIT業界で働けるチャンスは十分にあります。これからIT業界を目指す方にとって、SESは実践を通じてスキルを身につけられる良い選択肢となるでしょう。
エージェントの利用がおすすめ
未経験からSESとしてIT業界で働きたいと考えている方には、エージェントの利用をおすすめします。
未経験者にとっては、どの企業が育成に力を入れているのか、自分のスキルレベルで通用するかどうかを判断するのは簡単ではありません。エージェントは、そうした不安や疑問に対して、客観的な視点でサポートしてくれます。スキルや希望条件をもとに、成長環境が整った企業や未経験者歓迎の案件を紹介してくれるのが大きなメリットです。
また、求人の提案だけでなく、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、条件交渉まで幅広くサポートしてくれるため、転職活動そのものの質も高まります。とくにIT業界に特化したエージェントであれば、業界事情にも詳しく、よりマッチ度の高い企業と出会える可能性が高まるでしょう。
IT業界でSESとして働くならベスキャリITで
IT業界におけるSESという働き方は、スキルアップのチャンスや柔軟な働き方、人脈の広がりなど多くのメリットがあります。しかし、企業選びを誤るとブラックな環境に巻き込まれるリスクもあるため、SESの契約形態や実態を正しく理解し、自分に合った企業や案件をしっかり見極めることが重要です。
また、案件の自由度や報酬の高さ、働き方の柔軟性という点では、SESよりもフリーランスのほうが優れている可能性もあります。一定のスキルや経験を積んだエンジニアにとっては、フリーランスの方が「働き方」「収入」「キャリアの自由度」いずれの面でも満足度が高くなるでしょう。
ただし、フリーランスとして安定的に働くためには、案件選びや契約交渉、報酬管理など、多くの課題をクリアする必要があります。そんな時に頼りになるのが「ベスキャリIT」です。
ベスキャリITでは、SES案件はもちろん、高単価のフリーランス案件も豊富に取り扱っています。スキルや希望に合った最適な案件を紹介し、経験豊富なキャリアアドバイザーが案件選びから契約交渉、参画後のフォローまで丁寧にサポート。SESからのステップアップも安心して進められます。ぜひご登録ください。